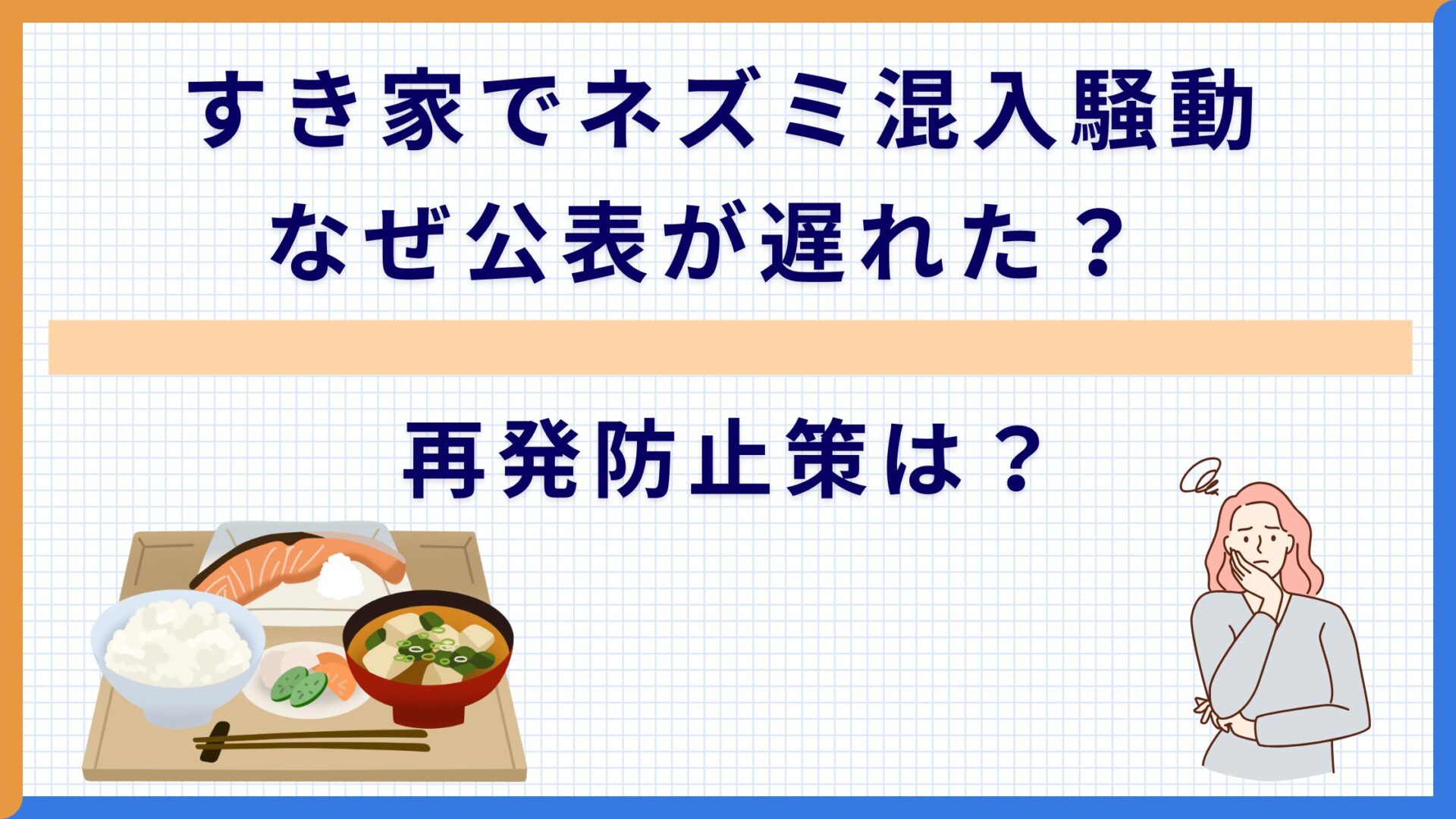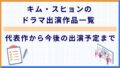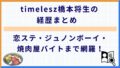2025年1月、すき家の味噌汁にネズミの死骸が混入していたという衝撃的な事件が発生し、SNSや口コミを通じて瞬く間に拡散されました。
特に、すき家が約2ヶ月にわたり公表を控えていた事実が明らかになり、消費者の間では不信感が広がっています。
本記事では、ネズミ混入の経緯と原因、公表が遅れた理由、そしてすき家が取った再発防止策について、詳しく解説します。
食品の安全性や企業の対応に不安を感じている方にこそ、ぜひ読んでいただきたい内容です。
興味がある方は以下の記事もどうぞご覧ください。
▶【速報】すき家でゴキブリ混入!全店一時閉店の異例対応とは?再発続く異物問題
すき家でネズミ混入が発覚|事件の経緯と詳細
すき家の「みそ汁」にネズミの死骸が混入していたという衝撃的なニュースが、SNSや口コミサイトを通じて広まりました。
問題が発覚したのは、2025年1月21日午前8時頃。
場所は鳥取県にある「すき家 鳥取南吉方店」です。
ある利用客が「たまかけ朝食」を注文した際、提供された味噌汁の中に明らかに異常な“異物”を発見。
その正体は、なんと丸ごとのネズミの死骸だったのです。
Googleレビューが火種に
この事件は、利用客がGoogleマップのレビューに写真付きで投稿したことにより、一気に拡散されました。
写真には、味噌汁の中に横たわるネズミの姿がはっきりと映されており、あまりにリアルなビジュアルにSNSでは「フェイク画像では?」「AIで作ったのでは?」という声も一部ありました。
しかし、のちにすき家の運営会社・ゼンショーホールディングスが事実を認めたことで、「本物の事件」として確定されました。
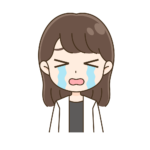
写真を見たのですが、かなりビックリしました。
提供された方は、かなりショックを受けたと思います。
すき家の公式発表と経緯の説明
ゼンショーは2025年3月22日、自社の公式ホームページで異物混入の事実と詳細な経緯、原因、再発防止策を公開しました。
公式によると、異物は味噌汁の具材を準備する段階で混入したとみられ、提供直前に従業員が目視確認を怠ったため、発見されることなく提供されてしまったとのことです。
問題発覚後は当該店舗を一時閉店し、衛生検査を実施。建物にクラック(ひび割れ)があったため、そこからネズミが侵入した可能性が高いとしています。
なぜネズミが混入したのか?
この点について、Yahoo!知恵袋などでは「どうしてそんなことが起こるのか?」という声が多く見られます。
結論から言うと、店舗の建物構造と周囲の環境に加え、人的なミス(確認不足)が重なった結果、ネズミが調理エリアにまで侵入し、準備中の食器に紛れ込んだと推定されます。
さらにネズミの死骸は加熱処理前に混入した可能性もあるため、従業員が盛り付けたあとに“そのままの形”で残っていたと考えられています。
すき家では、これまでにも衛生管理や異物混入対策に取り組んできたとされていますが、今回は防ぎきれなかったことを重く受け止めているとしています。
なぜすき家は約2ヶ月も公表を控えたのか?
今回の「ネズミ混入事件」において、多くの人々が驚いたのはすき家が事実を即座に公表しなかったことです。
事件が起きたのは2025年1月21日ですが、公式サイトで公表されたのは約2ヶ月後の3月22日。
この間、公式発表は一切なく、事件の詳細も不明なままSNS上で拡散されるのみとなっていました。
そのため、ユーザーの間では「隠ぺいでは?」「なぜこんなに遅れたのか?」といった疑問や怒りが高まっています。
発表の遅れは“混乱と不信感”を生む結果に
すき家の運営会社ゼンショーは、今回の公表遅れについて「断片的・間接的な情報が独り歩きし、お客様に不安と懸念を与えた」と認めています。
さらに、「発生当初に当社がホームページ等での公表を控えたことで、ご迷惑とご心配をおかけしました」と謝罪文も掲載しました。
これはつまり、事態が収束し原因がある程度特定されるまでは、あえて情報発信を控えていたことになります。
しかし結果的には、口コミから火がつき、SNSで拡散、そして大手メディアにも波及したことで、企業側の対応が「後手に回った」印象を残しました。
危機管理として適切だったのか?
このような「重大な食品事故」において、企業は通常、以下のような危機管理対応が求められます。
- 事実確認と初動対応
- 保健所など関係機関への報告
- 被害拡大の防止措置
- 消費者・社会への情報開示
ゼンショー側も、実際には当日中に保健所へ相談し、2日後には現地確認を受けたとしていますが、消費者への情報公開が著しく遅れたことは否定できません。
この遅延が、SNS上で「企業としての誠意が感じられない」「隠ぺい体質ではないか」といった厳しい意見を生む原因となりました。
SNSで拡がる“情報格差”とその影響
X(旧Twitter)やInstagramなどのSNSでは、この件に関して以下のようなコメントが多く見られました。
- 「画像が出回ってたのに、なんですき家は何も言わないの?」
- 「公式から説明ないと、もう食べに行けない」
- 「大企業なのにリスク管理が甘すぎる」
こうした“声”は、単なる炎上ではなく、現代の消費者が「透明性」や「即時性」を重視していることの表れでもあります。
企業の信頼性は、SNS時代において「説明責任をどう果たすか」によって大きく左右されるのです。
このように、すき家が約2ヶ月も情報開示を控えた背景には「確認中だった」「再発防止策を整えていた」といった事情があったかもしれませんが、それでも“公表の遅れ”は消費者の信頼を損なう結果となってしまいました。
今回の件は、飲食業界全体にとっても「情報公開の在り方」を考えさせられる重要な教訓となるでしょう。

飲食店街ではもちろん、住宅地でもネズミを見かけたことがあります。
飲食店で食事をしていたらネズミが走り回って騒ぎになったこともありました。
難しい問題ですね。
異物混入への再発防止策と今後の信頼回復策は?
今回の「ネズミ混入騒動」は、単なる一店舗のミスでは済まされない重大な問題です。
すき家を運営するゼンショーホールディングスは、事件の発生後すぐに店舗を一時閉店し、衛生検査や建物の確認、従業員教育の見直しなど、さまざまな再発防止策を講じたとしています。
では、具体的にどのような対応が取られたのか、また今後、信頼を回復するには何が必要なのかを見ていきましょう。
すき家が発表した主な再発防止策
ゼンショーが発表した公式対応の中で、注目すべき対策は以下の通りです。
- 当該店舗の即時閉店と衛生検査の実施
→ 問題発覚後、ただちに営業を停止し、第三者機関と連携して衛生状況をチェック。
- クラック(建物のひび割れ)の修復・調査
→ ネズミが侵入する要因となった可能性のある建物の隙間やひび割れを点検・修復。
- 商品提供前の目視確認を徹底
→ すべての店舗に対して、料理を出す直前の“最終確認”を義務付け。
- 従業員への衛生教育の再強化
→ 異物混入の可能性を減らすため、マニュアルの見直しと再研修を実施。
- 保健所との連携による営業再開の判断
→ 当該店舗は保健所の現地確認を経て営業再開しており、第三者の視点を入れた透明性も意識。
また、今後は全国のすき家店舗において、四半期ごとのクラック点検や、害虫・害獣対策の見直しも行うと明言しています。
ネズミの侵入経路が判明 冷蔵庫のパッキンが原因か
2025年3月29日、すき家は新たに発表を行い、ネズミ混入の侵入経路を特定したことを明らかにしました。
店内の防犯カメラ映像や現地調査をもとに、異物混入が発生した当日のうちに大型冷蔵庫の下部パッキンにひび割れがあり、そこからネズミが侵入した可能性が極めて高いと結論付けたとのことです。
さらに、問題の味噌汁を提供する際に使用されていたお椀は一時的に冷蔵庫内に保管されており、その保管中にネズミが混入した可能性が高いとしています。
これを受けて、ゼンショーは同型冷蔵庫を使用している全国72店舗でパッキンの状態を確認・修繕したことも明らかにしました。
今後は定期的な点検・保全により、同様のリスクを事前に回避していく方針です。
「鍋に混入した」説を否定 加熱されていなかったことが科学的にも証明
SNSでは「ネズミは味噌汁の鍋に入っていたのではないか」という疑惑の声も上がっていましたが、すき家はこの点について明確に否定しています。
店内カメラの映像には、ネズミが具材を入れる前のお椀の中に混入した様子のみが映っていたとのこと。
問題があったのは1つのお椀だけで、味噌汁を煮ていた鍋の中に混入する場面は確認されていませんでした。
さらに、すき家の食品安全基準本部が実施したカタラーゼ検査の結果、混入していたネズミの死骸は加熱処理されていなかったと判明。
加熱されたタンパク質では反応が出ないため、この検査で“鍋で煮込まれた可能性”が極めて低いことが科学的に裏付けられました。
ネズミの習性として熱に非常に敏感であるため、沸騰した鍋に自ら飛び込む可能性はきわめて低いという専門的見解も付け加えられています。
このように、すき家は映像と科学的検証の両面から「鍋混入説」を否定しており、信頼回復の一環として情報の透明性を高めています。
類似事例と“業界全体”の課題
実は、今回の事件だけではなく、近年は大手食品メーカーや学校給食でも同様の異物混入事件が発生しています。
- 2024年:大手製パン会社の食パンからクマネズミの一部が見つかり、約10万個を自主回収
- 2023年:東京都内の中学校給食にネズミの糞が混入
- 2022年:某製菓会社の焼き菓子に異物混入が発覚
このように、食品を取り扱う現場では、どれだけ対策をしていても「100%の防止」は難しいという現実もあります。
しかしそれでも、発生した際の対応スピードと、情報公開の姿勢が信頼性を大きく左右するのです。
今後の信頼回復に必要なことは?
すき家が再発防止策を講じたとはいえ、消費者の不安がすぐに払拭されるわけではありません。
信頼を取り戻すには、一過性の対応ではなく、継続的で透明な努力が求められます。
たとえば以下のような姿勢が今後カギになるでしょう。
- 定期的に衛生状態を開示する(例:点検状況・報告書の一部公開)
- 「食の安全」をテーマにした公式発信を強化する
- SNSやレビューサイトでの顧客の声に敏感に対応する
- 店舗スタッフの衛生意識向上を目的とした“見える化”
すき家は、庶民にとって“手軽に入れる飲食店”であり、家族や学生にも人気のブランドです。
その信頼を裏切ることがないよう、これからの行動と実績が大切になるでしょう。
まとめ
すき家で起きたネズミ混入事件は、単なる一飲食店の問題ではなく、食の安全や企業の危機対応が問われる象徴的な事例となりました。
情報公開の遅れがさらなる不信を招いた一方で、再発防止策の強化や衛生対策への取り組みは一定の評価を受けています。
飲食業界全体が安全管理の在り方を見直す中、今後すき家がどのように信頼を取り戻していくのか、その動向が注目されます。
私たち消費者も、情報を正しく見極めながら、企業の対応を冷静に見ていくことが大切です。
興味がある方は以下の記事もどうぞご覧ください。
▶【速報】すき家でゴキブリ混入!全店一時閉店の異例対応とは?再発続く異物問題