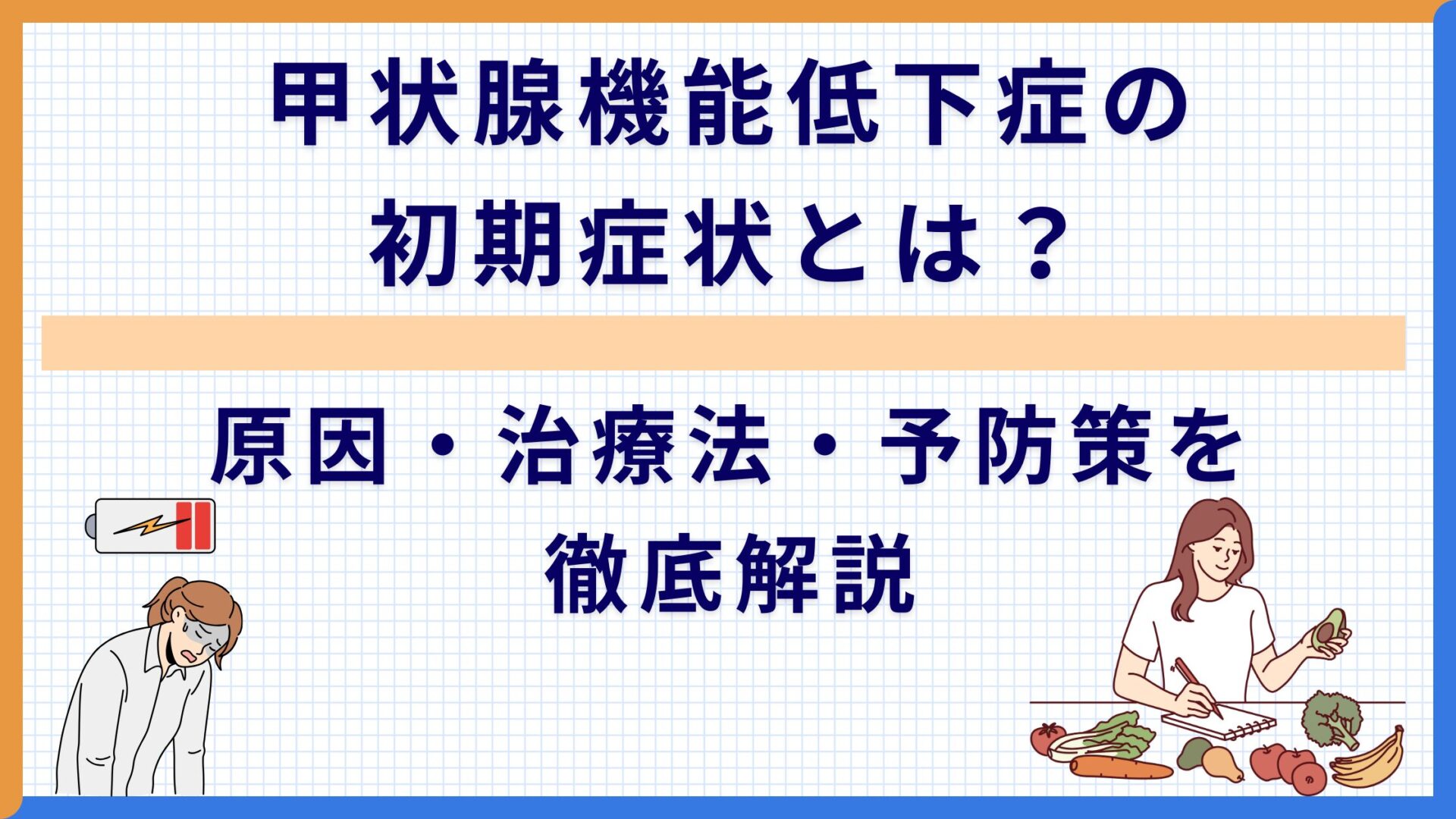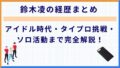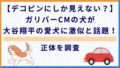「最近、疲れやすい」「寒がりになった」「体重が増えやすい」──このような症状が続いていませんか?
もしかすると、それは 「甲状腺機能低下症」 のサインかもしれません。
甲状腺機能低下症は、甲状腺ホルモンが不足することで代謝が低下し、全身の機能に影響を与える病気 です。
しかし、その症状が更年期障害やうつ病と似ているため、気づかずに放置してしまう人も少なくありません。
この記事では、甲状腺機能低下症の初期症状や原因、治療法、予防策について詳しく解説 します。
早期発見と適切な治療で症状を改善し、健康的な生活を取り戻しましょう。
甲状腺機能低下症とは? 初期症状と見分け方
甲状腺ホルモンが不足するとエネルギー代謝が低下し、全身の機能に影響を与える病気です。
甲状腺の役割と甲状腺機能低下症の仕組み
甲状腺はのどの中央付近にある小さな臓器で、蝶が羽を広げたような形をしています。
この甲状腺は 甲状腺ホルモン を分泌する役割を担っており、体のさまざまな臓器の新陳代謝を調節しています。
甲状腺ホルモンは、脳の下垂体から分泌される「甲状腺刺激ホルモン(TSH)」の指令によって生成されます。
ところが、何らかの原因で甲状腺の機能が低下すると、ホルモンの分泌が減少し、エネルギー代謝が低下します。
この状態を甲状腺機能低下症といいます。
甲状腺機能低下症の初期症状
甲状腺ホルモンの分泌が不足すると、エネルギー代謝が低下し、体にさまざまな影響が出ます。
特に初期症状として次のようなものが挙げられます。
- 疲れが取れにくくなる(以前よりも疲労感が抜けにくい)
- 食事量が変わらなくても体重が増えやすくなる
- 顔や手足がむくみやすくなる
- 寒さを感じやすくなる(周囲の人が寒くない環境でも冷えを感じる)
- 動作や話すスピードが遅くなる(動きが鈍くなり、会話のテンポがゆっくりになる)
- 物忘れが増え、集中しにくくなる(記憶力や注意力が低下する)
- 便秘になりやすくなる(腸の動きが鈍くなり、排便が困難になる)
- 肌が乾燥しやすくなる(潤いが減少し、カサつきやすくなる)
- 声がかすれる(嗄声(させい)が現れ、声がしわがれる)
こうした症状が現れても、風邪や加齢、更年期障害、ストレスの影響と勘違いされることが多く、甲状腺機能低下症に気づかないケースが少なくありません。
甲状腺機能低下症が進行するとどうなる?
軽度の場合、自覚症状がほとんどないこともありますが、進行すると「粘液水腫(ねんえきすいしゅ)」と呼ばれる状態になり、深刻な症状が現れることがあります。
- 極端な無気力感や意識障害
- 体温の異常な低下(低体温)
- 重度のむくみ(顔や手足が腫れる)
- 心拍数の低下(脈が遅くなる)
さらに 「粘液水腫性昏睡(こんすい)」 という状態に陥ると、生命の危険が伴うため、早急な治療が必要になります。
甲状腺機能低下症と他の病気との違い
甲状腺機能低下症の症状は、更年期障害やうつ病、貧血などの症状と重なる部分が多いため、自己判断が難しい病気 です。
例えば、更年期障害ではホルモンバランスの変化によるほてりや発汗、動悸が目立ちますが、甲状腺機能低下症ではむくみや寒がり、動作の緩慢さが特徴的です。
また、うつ病の場合、精神的な落ち込みや意欲の低下が中心ですが、甲状腺機能低下症では 身体的な症状(むくみ・便秘・体重増加など) が伴うことが多くあります。
疑わしい場合は早めに医療機関を受診しましょう
甲状腺機能低下症は、血液検査によって診断できます。
具体的には、甲状腺ホルモン(T3・T4)や甲状腺刺激ホルモン(TSH)の数値を確認することで、甲状腺の機能が正常かどうかを判断します。
甲状腺機能低下症は、適切な治療を行えば改善が期待できる病気です。
疲れやすさやむくみ、寒がりなどの症状が続く場合は、早めに内分泌内科や内科を受診しましょう。
甲状腺機能低下症の原因と発症しやすい人の特徴
甲状腺機能低下症にはさまざまな原因があり、特定の人に発症しやすい傾向があります。
ここでは、主な原因とリスクの高い人の特徴について解説します。
甲状腺機能低下症の主な原因
甲状腺機能低下症の原因は、大きく分けて 「原発性甲状腺機能低下症」、「中枢性甲状腺機能低下症」、「甲状腺ホルモン不応症」の3つのタイプがあります。
1. 原発性甲状腺機能低下症(甲状腺に原因がある)
原発性甲状腺機能低下症は、甲状腺自体の機能低下により、ホルモンの産生が不足する病気です。
その中でも、最も一般的なのが「慢性甲状腺炎(橋本病)」とされています。
- 慢性甲状腺炎(橋本病)
甲状腺に慢性的な炎症が起こり、機能が低下する病気です。自己免疫疾患の一種で、体内で作られた抗体が甲状腺を攻撃することにより発症 します。- 甲状腺が腫れることがあり、首に違和感を覚える
- 甲状腺の働きが低下すると、疲れやすさやむくみ、寒がりなどの症状が現れる
- ヨウ素(ヨード)の過剰摂取
ヨウ素は甲状腺ホルモンの材料ですが、過剰に摂取すると逆に甲状腺機能が低下することがあります。特に昆布や海藻を大量に摂取する人は注意が必要です。
- 甲状腺の手術や放射線治療の影響
甲状腺がんや甲状腺の病気で手術を受けた人、放射線治療を受けた人は、甲状腺の機能が低下しやすくなります。
- 先天性甲状腺機能低下症(クレチン症)
生まれつき甲状腺がうまく機能しない場合もあります。この場合、成長や発達に影響を与えるため、新生児期の早期発見が重要 です。
2. 中枢性甲状腺機能低下症(脳に原因がある)
甲状腺ホルモンの分泌は、脳の 下垂体や視床下部 がコントロールしています。
これらの部位が正常に機能しないと、甲状腺ホルモンの分泌が低下します。
- 脳腫瘍や脳出血(くも膜下出血など)
- 脳外科手術の影響
- 自己免疫性下垂体炎 など
これらの原因により下垂体や視床下部がダメージを受けると、TSH(甲状腺刺激ホルモン)の分泌が乱れ、甲状腺の機能が低下します。
3. 甲状腺ホルモン不応症(ホルモンがうまく作用しない)
このタイプは、甲状腺ホルモンが正常に分泌されていても、体の細胞がホルモンに適切に反応しないことで起こる病気 です。
遺伝的な要因が関係しており、日本では 100人未満の患者しかいないとされる非常にまれな疾患 です。
甲状腺機能低下症になりやすい人の特徴
甲状腺機能低下症は 特定の人に発症しやすい傾向 があります。
次のような特徴に当てはまる人は、注意が必要です。
1. 女性である
甲状腺機能低下症は女性に多く、男性の約10〜30倍の割合で発症するといわれています。特に30〜40代の女性に多く見られ、更年期以降の女性もリスクが高まります。
2. 家族に甲状腺の病気の人がいる
橋本病などの甲状腺疾患は遺伝的な要因が関係していることがあります。家族に甲状腺の病気を持つ人がいる場合、自分も発症するリスクが高くなります。
3. ヨウ素を過剰に摂取している
昆布や海藻を頻繁に食べる人、ヨウ素を多く含む健康食品を摂取している人は、甲状腺機能低下症を引き起こす可能性があります。
4. 甲状腺の手術や放射線治療を受けたことがある
甲状腺がんやバセドウ病の治療で 甲状腺を摘出したり、放射線治療を受けたりすると、ホルモンの分泌が減少し、甲状腺機能低下症を発症する可能性 があります。
5. 妊娠・出産を経験している
出産後に 「産後甲状腺炎」 を発症することがあります。これは、妊娠中に免疫機能が変化し、産後に甲状腺に炎症が起こることが原因です。
6. 加齢によってリスクが高まる
年齢が上がると 潜在性甲状腺機能低下症(自覚症状がほとんどないがホルモンのバランスが崩れている状態) が増加します。特に高齢の女性は注意が必要です。
甲状腺機能低下症の発症リスクと原因まとめ
甲状腺ホルモンが十分に供給されないことで、エネルギー代謝が低下し、体にさまざまな影響を与える病気です。
特に 橋本病(慢性甲状腺炎) や ヨウ素の摂りすぎ などが原因となることが多く、女性や家族に甲状腺疾患の人がいる場合は発症リスクが高まります。
この病気は 進行すると深刻な症状を引き起こす可能性があるため、早期発見が重要 です。
次の章では、甲状腺機能低下症の治療法と予防策 について詳しく解説します。
甲状腺機能低下症の治療法と予防策
甲状腺機能低下症は、適切な治療を受けることで症状を改善できます。
また、日頃の生活習慣を見直すことで予防することも可能です。
甲状腺機能低下症の治療法
甲状腺機能低下症の治療は、不足している甲状腺ホルモンを補充すること が基本です。
主に ホルモン補充療法(内服薬) が行われます。
1. ホルモン補充療法(チラーヂン®S)
甲状腺ホルモンを補うために、「チラーヂン®S(レボチロキシンナトリウム)」 という合成T4製剤が処方されます。
この薬を服用することで、甲状腺ホルモンの不足を補い、症状を改善できます。
- 服用方法
- 朝の空腹時 にコップ1杯の水と一緒に服用する
- ほかの薬と併用する場合は時間を空ける(鉄剤や胃薬は吸収を妨げるため注意)
- 服用量の調整
- 治療開始時は 少量から服用し、徐々に増やしていく
- 維持量(通常50~150μg/日) に達するまで、数か月かけて調整する
- 高齢者や心臓病のある人は 慎重に投与 する
- 服用をやめてはいけない
甲状腺機能低下症の多くは 慢性疾患のため、生涯にわたって治療が必要 です。症状が改善しても 自己判断で薬を中止すると、再び症状が悪化する ため、医師の指示に従うことが重要です。
2. 軽度の甲状腺機能低下症(潜在性甲状腺機能低下症)の治療
甲状腺ホルモン値は正常範囲内だが、TSH(甲状腺刺激ホルモン)が高値である場合を 「潜在性甲状腺機能低下症」 といいます。
この場合、必ずしも治療が必要ではありませんが、次のような場合は薬による治療が推奨 されます。
- TSHが一定値以上(10μU/mL以上)に高い場合
- 妊娠中、または妊娠を希望している場合(流産や胎児の発育に影響を与えるため)
- 症状が強く日常生活に支障がある場合
軽度の場合、経過観察を行いながら、必要に応じて治療を開始します。
3. 中枢性甲状腺機能低下症の治療
脳の下垂体や視床下部が原因で起こる 「中枢性甲状腺機能低下症」 の場合も、基本的にはホルモン補充療法 が行われます。
ただし、脳腫瘍や脳出血などが原因となるため、場合によっては 外科手術や放射線治療 が必要になることもあります。
甲状腺機能低下症を予防するための生活習慣
甲状腺機能低下症を完全に防ぐことは難しいですが、生活習慣を見直すことでリスクを減らすことができます。
1. ヨウ素の摂取量を適切にする
ヨウ素は 甲状腺ホルモンの材料 ですが、摂りすぎると逆に甲状腺機能を低下させる ことがあります。
- 過剰摂取を避けるべき食品
- 昆布やわかめ、ひじき、もずくなどの 海藻類
- 昆布だし、昆布エキスが含まれる食品
- ヨウ素を含む健康食品(根昆布エキスなど)
一方で、極端なヨウ素不足も甲状腺ホルモンの分泌に影響を与えるため、適量を意識することが大切 です。
2. 定期的に甲状腺の検査を受ける
特に 女性や甲状腺疾患の家族歴がある人 は、定期的に血液検査を受けることをおすすめします。
- 甲状腺ホルモン(T3・T4)の値を測定
- TSH(甲状腺刺激ホルモン)の値を確認
症状がない場合でも、早期発見が重要 です。
3. ストレスをためない
ストレスは 自律神経のバランスを乱し、甲状腺ホルモンの分泌に影響 を与えることがあります。
- 十分な睡眠をとる(7~8時間の睡眠が理想)
- 適度な運動をする(ウォーキングやストレッチがおすすめ)
- 趣味やリラックスできる時間を作る
特に 更年期の女性はホルモンバランスが変化するため、ストレス管理が重要 です。
4. バランスの良い食事を心がける
甲状腺ホルモンの働きを助ける栄養素を意識的に摂取することも大切です。
- 鉄分(レバー、赤身の肉、ほうれん草など)
- 亜鉛(牡蠣、ナッツ類、牛肉など)
- セレン(魚介類、ナッツ類など)
ただし、サプリメントの過剰摂取には注意 しましょう。
甲状腺機能低下症の改善策とは?
甲状腺機能低下症は、ホルモン補充療法(チラーヂン®S)による治療が基本です。
適切に治療を継続すれば、日常生活に大きな支障なく過ごすことができます。
また、ヨウ素の摂取量を適切に管理し、ストレスを減らし、定期的な検査を受けることで、甲状腺の健康を維持しやすくなります。
疲れやすい、むくみが気になる、体重が増えやすいなどの症状がある場合は、早めに医療機関を受診しましょう。
甲状腺機能低下症の予防と対策まとめ
甲状腺機能低下症は、甲状腺ホルモンが不足することで代謝が低下し、さまざまな不調を引き起こす病気 です。
疲れやすさやむくみ、体重増加、便秘などの症状が現れ、進行すると意識障害などの重篤な状態に陥ることもあります。
主な原因は 橋本病(慢性甲状腺炎)やヨウ素の過剰摂取 などで、特に 女性や家族に甲状腺疾患がある人は発症リスクが高い とされています。
治療には 甲状腺ホルモン補充療法(チラーヂン®Sの服用) が用いられ、適切に治療を続ければ症状の改善が期待できます。
予防するには、ヨウ素の摂取量を適切に管理し、ストレスを減らし、定期的に甲状腺の検査を受けることが大切です。
疲れやすさやむくみなどの症状が続く場合は、早めに医療機関を受診しましょう。